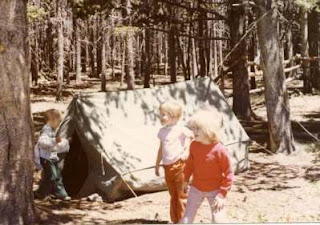ただいま。私は幕別町の中学生14人、高校生2人、引率者2人と一緒に春休み中の海外研修に行って参りました。10日間、心地よい日本の幕別町と家族から離れて外国の生活を味わってきました。例年のようにオーストラリア・キャンベラ市のカンバー高校を目的地に、3月28日とかち帯広空港を旅立ちました。そして、4月7日に家族・先生・友達の出迎えお受け、皆無事に帰りました。
View Larger Map
この研修は個人的にも非常に良い経験となり、勉強になりました。同じ「英語圏」ですが、やっぱり違います。表現と言葉や発音と抑揚の違いで私にも (オーストラリアで話す英語)は時に分かりにくいものでした。生徒には、分かりにくかったでしょうか。私は、3年間日本語を勉強してから北海道で生活した経験があります。当時の同僚と一緒に青森を旅したことがあります。東北弁にたいして同僚が「それは日本語じゃない」と言っていましたが、私には北海道弁やら東北弁やらあまり関係はありませんでした。知らない言葉が殆どだったため、3年間で覚えた基礎日本語を聞き取って、文脈から推測して理解しようとしていました。きっと生徒は似たような経験をしてきたでしょう。色々な言語の違いがあっても分からないわけでもないし、ちょっとした確認で相手が言い換えてくれます。私が一番使った“確認するための英語”を教えてあげましょう。とても簡単です。これは、文章は分かったけれど、重要な単語一つが聞き取れなかった場合に使う“確認するための英語”です。
「What’s ~」(~は何ですか?)
「~」のところに聞き取った知らない単語をそのまま言い返します。私のホームスティの方が「ジャイル」について話してくれましたが、その言葉がわからなくて、「What’s a ジャイル?」と確認してみたら「You know, a penitentiary, a place where they put people who’ve broken the law.」と説明してくれました。彼が説明していた言葉は「jail」でした。アメリカの発音でしたら「/ジェイル」になりますが、Aussie Englishでは「áil/ジャイル」でした。
この研修を通して改めて分かったことがあります。前にもこの欄で書いたことがありますが、コミュニケーションは口で言える言葉や耳で聞こえる言葉だけではなく、目で見えるもの、五感で感じるもの、身振り手振りや顔の表情等、色々な方法で行うことだと思います。そして、いつも皆の耳にたこが出来るほど言えば、今現在、自分の持っている英語でコミュニケーションが取れます。七転八起。いろんな方法から攻めてみることが大切です。言葉が通じなかったら、違う言葉で言ってみよう。適切な表現が分からなかったら、自分が知っている言葉から攻めて見ます。大きい木は大きな一振りで倒せません。諦めずに、小さい言葉から一杯振って見てください。
最後に覚えてきたAussie Englishを少し紹介したいと思います。
G’day (グデイ)=こんにちは Arvo (アルボー)= 午後 Oz (アズ)=オーストラリア Footy (フティー)=アーストラリアのフットボール Lolly (ロリー)=キャンディー Tea (ティー)=夕食、食事 Mate (メイットゥ)=あなた、友達 Sunnies (サニーズ)=サングラス
一番最後にNo worries! =問題ない、大丈夫です、どういたしまして
キャンベラ【Canberra】オーストラリア連邦の首都。同国南東部の内陸にある。人口29万8千(1993)。